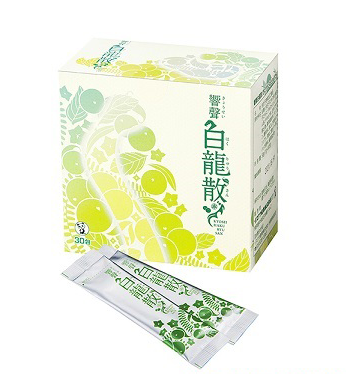響聲白龍散(きょうせいはくりゅうさん)
高品質漢方薬で有名なイスクラ産業(株)より、のどにおすすめの健康食品、響聲白龍散(きょうせいはくりゅうさん)が発売されました。
響聲白龍散(きょうせいはくりゅうさん)は、スッキリした清涼感が特徴的です。
のどをよく使う方やのどの調子が良くない、のどが痛い、という方はもちろん、声がかれてしまう方、エヘンという咳をしてしまう方、のどに詰まり感を感じる方におすすめの健康食品です。
余甘子(ヨカンシ)をはじめ、桔梗(キキョウ)、真珠(シンジュ)、銀耳(ギンジ)、甘草(カンゾウ)、緑茶、ハッカ油を配合した健康食品です。
水なしで飲める発泡顆粒タイプ。
余甘子の酸味とハッカ油の清涼感でのどスッキリ。ボイスケアにオススメです。
響聲白龍散(きょうせいはくりゅうさん)の構成生薬
★ 余甘子(ヨカンシ) ★
【別名】油柑(ユカン)、アムラ、マラッカノキ、インディアン・グーズベリー。ルチン・タンニンなどのポリフェノールを含有する余甘子(ヨカンシ)は、トウダイグサ科(またはミカンソウ科)の落葉高木の果実です。熱に強いビタミンCや食物繊維のペクチンも豊富に含まれていて、抗酸化作用に優れています。
抗酸化作用が優れている裏付けになるでしょうか、古くからインドのアーユルヴェーダにおいては「若返りの果実」と言われ、滋養強壮もあるとして人気があったようです。
余甘子(ヨカンシ)の果実はそのままでは酸味・苦味・渋味がありますので、一般的には塩やスパイスなどでアチャール(漬物)にしたり、砂糖を加えて煮詰めて漬けたものを食べて健康維持に役立てているようです。
★ 桔梗(キキョウ) ★
【別名】岡止々支(おかととき)、きちこう、あさがお。キキョウ科の多年草の植物で、根の部分(桔梗根)が生薬として使用されます。秋の七草としても有名で、また、清和源氏系で、土岐氏とその一族の家紋は桔梗紋ですね。万葉集では「あさがお」と詠まれ、日本でも古くから愛されている植物のひとつです。
桔梗根は、肺の機能を高めて、痰を取り除く宣肺去痰(せんぱいきょたん)が特徴です。他に抗炎症作用、免疫力アップ、鎮静・解熱作用があるとされています。
開宣肺気・去痰・排膿で、のどの腫れや咳に石膏と組み合わせた桔梗石膏という漢方処方もあります。
また、桔梗は引経薬といって、肺から上へ薬を導く作用があるとされています。寒熱両方に適応できます。のどが痛む風邪薬の「天津感冒片(てんしんかんぼうへん)」や「銀翹散(ぎんぎょうさん)」にも配合されている生薬です。
★ 真珠(シンジュ) ★
【別名】珍珠、れんじゅ。ウグイスガイ科アコヤガイ、イシガイ科シナカラスガイにて作られる球体。基本的に天然ものでも養殖ものでも、装飾品にならないものを生薬として用います。
清肝明目(肝火を冷まし視力を明瞭にする)、鎮心安神(精神を安定させる)、清熱解毒生肌(熱を冷まし、湿疹や傷の修復を促す)といった作用に優れています。咽頭炎・口内炎・歯肉炎などには牛黄と一緒(珠黄散)に外用に使用することもあります。
肝火にはオウゴン・菊花・石決明・青葙子(セイソウシ)と共に配合した七宝散という処方があり、癲癇や痙攣には、黄連・琥珀・胆南星・牛黄と共に配合した金箔鎮心丸という処方があります。
★ 銀耳(ギンジ) ★
【別名】白きくらげ。白木耳。シロキクラゲ科シロキクラゲ属のキノコです。昔は銀と同じくらい貴重だったので、銀耳という名前がついたとか。台湾ではハスの実と白キクラゲのスープ、蓮子銀耳湯がコンビニでも買えるそうです。
銀耳は、血中コレステロールを低下させる効果が高いとされていて、動脈硬化や心疾患の予防等に活用される他、お肌ぷるぷる身体に潤いを与えるとして薬膳でも人気が高く、特に空気が乾燥する春秋のドライシンドロームの時期には大人気です。
滋陰潤肺、養胃生津。
★ 甘草(カンゾウ) ★
【別名】蜜草、生草。マメ科の多年草。主に根を乾燥させたものを使用します。甘草そのままを加熱加工もしくは甘草の蜂蜜漬けは炙甘草といいます。
解毒作用のあるトリテルペノイド配糖体のグリチルリチン、抗アレルギー作用のあるフラボノイドとしてリキリチンなどを含有しています。
益気補中・去痰止咳・清熱解毒・抗炎症などが特徴で、特に急な痛みを緩和するので非常に役立つ生薬といえるでしょう。
甘草が含まれた漢方処方は非常に多く、薬味の調和に用いる事も多くあります。
★ 緑茶 ★
【別名】チャ、煎茶、ほうじ茶、玉露、かぶせ茶、日本茶、等々。ツバキ科チャノキの葉を加熱処理した後、不発酵させたもの。日本では煎茶、ほうじ茶、玉露など、栽培方法によって呼び名が変わりますが、全て緑茶です。
不発酵茶が緑茶になり、弱発酵茶は白茶や黄茶、半発酵茶はウーロン茶、完全発酵茶が紅茶、後発酵茶が黒茶になります。
中国ではもっと種類が豊富にあり、加工方法や味わいも多岐に渡ります。最高級茶の黄山雀舌(こうざんじゃくぜつ)、春茶を釜で乾燥させ香りと味が濃厚な台湾龍井(たいわんろんじん)、臨済宗の開祖である栄西禅師が日本に持ち帰ったとされる清々しい香りの徑山茶(けいざんちゃ)など、銘茶がたくさん!機会があれば是非、中国緑茶も味わってみてくださいね。
緑茶の成分としては、渋味のもとタンニン(カテキン:血中コレステロール低下、抗菌、抗酸化)、苦味のもとカフェイン(気分をスッキリさせるアミノ酸の一種)、カリウム(ナトリウムによる血圧上昇を抑制)、ビタミンC(疲労回復、美肌、抗ストレス)
の他、旨味のもとテアニン(血圧上昇抑制、脳神経調節)は煎茶やほうじ茶より玉露や抹茶のほうが多く含まれています。
★ 薄荷(ハッカ) ★
【別名】蘇荷、ト荷、ペパーミント、メントール、などなど。紫蘇科の多年草。葉や地上部が薬用として使用されます。漢方では主に解熱や清涼、健胃を目的として使用される生薬です。
発熱や喉の痛み、軽めの悪寒などを改善する疏散風熱、熱感のある頭痛を改善する清利頭目、目や喉の腫れ、充血を改善する利咽、皮疹のかゆみなどを改善する透疹、胸の腫れや苦しい痛みを改善する疏肝解鬱が特徴です。
1855年~は、日本でも薄荷栽培がされていましたが、現代では北海道で数軒の農家が生産されているようです。
ティー、リキュール、ガム、飴、チョコレート、ゼリーなどの食品から、石鹸、シャンプー、アロマ、芳香剤、入浴剤、湿布、胃腸薬、目薬、鎮痛剤など、活用範囲は多岐に渡ります。
自分に合っていないものを服用しても効果がでないばかりか、症状を悪化させることもあります。
あなたにピッタリの漢方薬・オリエンタルハーブをお選びいたします。
ご利用の際は当店にお気軽にご相談ください
関連記事
-

-
自律神経を整えよう
春になると、「そわそわとして気持ちが落ち着かない」「衝動的な感情をコントロールし …
-

-
花粉症の食養生
今月は【花粉症の食養生】をご紹介します。 花粉症は免疫システムの不調和によるもの …
-

-
松寿仙しょうじゅせん
自然治癒力を高める本物の自然薬 私たちの体には、本来、生体機能のバ …
-
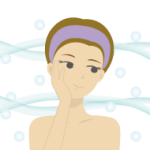
-
美肌のつくりかた
お肌は何でできている? もっと美しくなりたい・・・100年前も1000年前もずっ …
-

-
低体温と妊活
万病のもととなる低体温 日本人の平均体温がだんだんと低くなってきている事はご存じ …
-

-
何色ですか?あなたの風邪
どんなに気をつけていても、風邪を引いてしまう時、ありますよね? そんな時は風邪の …
-

-
暑気あたり漢方
まだまだ暑い日が続いておりますが、夏とはいえ、体温超えの気温にはさすがに驚きます …
-

-
口内炎
梅雨から初夏に多いご相談に口内炎があります。 口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎 …
-

-
デング熱、マダニ、MERS
デング熱、マダニ、MERS(マーズ)コロナウイルス 昨年の夏、160名を超える感 …
-

-
ニキビでわかる五臓のヘルプサイン
どこにニキビができていますか? 中医学(中国漢方)では、皮膚は内臓の鏡といいます …